物流の効率化が社会全体の課題となっている中、複数の運送手段を組み合わせて荷主の多様なニーズに応える「 貨物利用運送事業 」が注目されています。近年では、単一のトラック運送では対応が困難な広域輸送や大量輸送のニーズに対して、鉄道や海運を組み合わせることで、より安定的かつ効率的な輸送体制を構築できる点が評価されています。
「 貨物利用運送事業 」とは、荷主との運送契約により、国内外を問わず、陸海空のうち最適な輸送手段を利用して貨物の集荷から配達までを一貫して行う輸送サービ スです。鉄道や海運では大量輸送貨物を、航空や自動車では生鮮食料品や機械部品などの時間に制約のある貨物というように各々の輸送手段の特性を生かした輸送モードを選択し、荷主の要請に応えることができます。
さらに、貨物利用運送事業の機能は、単に実運送を補完するばかりではなく、物流に対する様々な荷主のニーズに対応した輸送サービスの実現を実運送事業者 に対し求めていくという積極的な役割が期待されています。
この貨物利用運送事業には、大きく分けて「 第一種貨物利用運送事業 」と「 第二種貨物利用運送事業 」の2種類があり、それぞれ法的な手続や要件が異なります。第一種は「登録制」、第二種は「許可制」とされており、それぞれ事業の性質や規模に応じた手続が求められます。
本記事では、これら貨物利用運送事業の登録・許可制度について、行政書士の立場からわかりやすく解説していきます。特に、第一種と第二種の違い、必要書類や約款認可の注意点、外国法人による申請の留意点、承継や廃止の際の手続など、実務上重要なポイントを網羅的に取り上げます。
貨物利用運送事業に新規参入したい事業者や、すでに事業を行っていて制度改正や更新手続に悩まれている方にとって、実務で活用できる情報を提供することを目的としています。
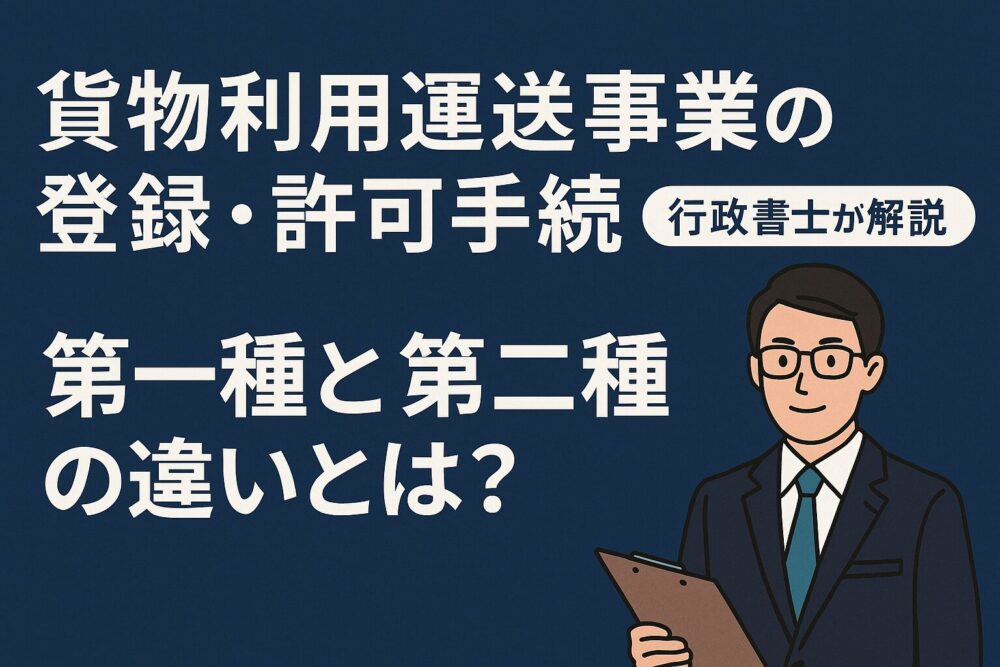
貨物利用運送事業 第一種 と 第二種 の違い
貨物利用運送事業には「第一種」と「第二種」の2類型があり、それぞれに異なる法的枠組みが設けられています。この違いは、手続の区分(登録制か許可制か)だけでなく、業務内容や施設・財産基盤に対する要件の厳しさにも現れています。
第一種 貨物利用運送事業 とは
第一種貨物利用運送事業は、主に中小規模の事業者が対象となる制度であり、「 登録制 」によって運営されています。実際の運送業務を外部の実運送事業者(例:トラック業者や海運会社)に委託し、自らは運送手段を保有せず、運送契約の仲介・管理などの機能を担います。
第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
貨物利用運送事業法 第3条
第一種事業では、貨物の集配や保管といった「物理的な取り扱い」を伴わない場合も多く、保管施設を持たない形態でも登録が可能です。一方で、最低限の事務所等の施設は必要とされており、また財産的基礎として「300万円以上の資産」が求められます。
登録申請にあたっては、登記事項証明書、事業計画書、契約書の写し、財産調書など、多くの添付書類が必要です。
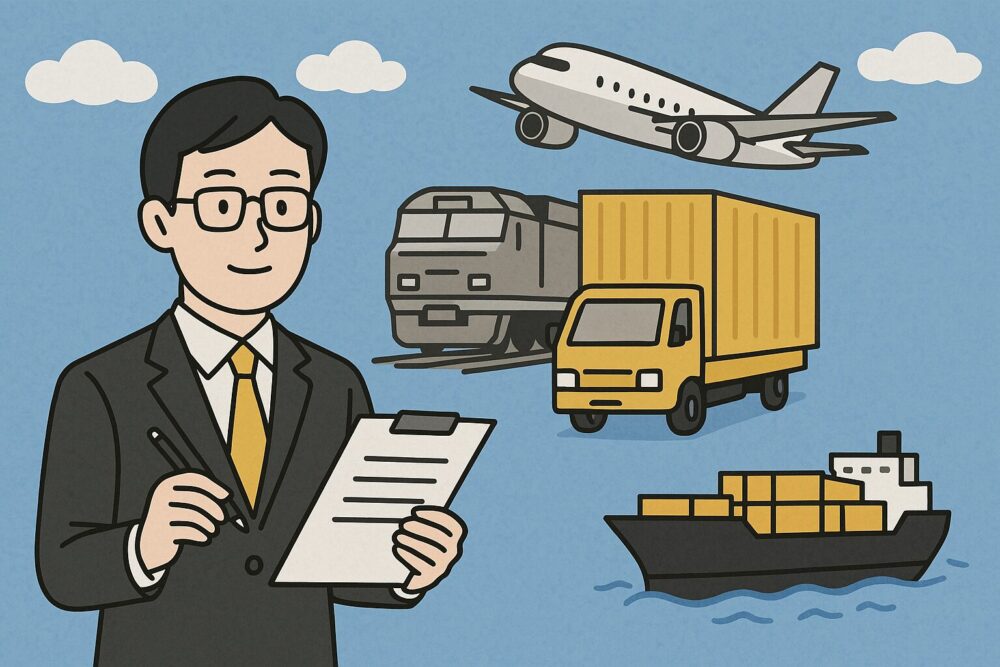
第二種 貨物利用運送事業 とは
第一種貨物利用運送事業に対して、第二種貨物利用運送事業は、より包括的な運送管理を行う事業者が対象であり、「 許可制 」となっています。第一種との最大の違いは、荷主の依頼に応じて貨物の「集配」や「保管」を伴う業務を含む点にあります。実際の運送に加え、貨物をトラックで集めて中継拠点に運んだり、鉄道・海運に載せたりするまでの一連の工程を担う役割が求められるのです。
この法律において「 第二種貨物利用運送事業 」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送(「貨物の集配」)とを一貫して行う事業をいう。
貨物利用運送事業法 第2条第8項
第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
貨物利用運送事業法 第20条
このため、第二種では貨物の保管施設や、自動車を使って集配を行う場合の運行管理体制・車両数・車庫の収容能力・運転者の休憩施設など、非常に詳細な計画の提出が必要とされます。特に、自動運行貨物運送(自動運転車両を活用した運送)を行う場合は、さらに追加の技術的書類も必要となります。
また、第二種事業者には「業務の範囲」や「区域」なども事業計画において明確にしなければならず、事業規模に見合った人的・物的体制が審査されます。これは単に「許可制」であるというだけでなく、継続的に高度な運営能力を求められる点で、第一種よりもはるかに重い要件となっています。
貨物利用運送事業 第一種 第二種 比較のまとめ
| 区分 | 第一種 | 第二種 |
|---|---|---|
| 手続 | 登録制(法第3条) | 許可制(法第20条) |
| 業務内容 | 運送手配・契約管理中心 | 運送+集配・保管も実施 |
| 必要施設 | 事務所(保管施設は任意) | 保管施設、車庫、休憩施設など必須(施行規則第18条) |
| 財産基盤 | 300万円以上の資産(施行規則第7条) | 同様(施行規則第19条)だが事業計画の網羅性が必要 |
| 履行体制 | 比較的簡易 | 非常に詳細で高度 |
このように、第一種と第二種の違いは単なる呼称の問題ではなく、実質的な業務範囲や求められる責任に直結します。事業者としてどちらを選択するかは、想定する物流規模や顧客ニーズに応じて慎重に検討すべきでしょう。
貨物利用運送事業 申請手続きについての行政書士報酬は
申請ALL.com ならチャットボットで自動でお見積りいたします。
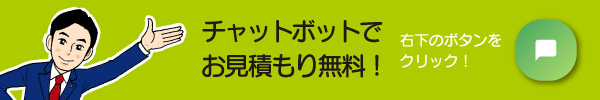
貨物利用運送事業 登録・許可手続の具体的な流れ
貨物利用運送事業を開始するには、第一種・第二種いずれの類型であっても、所定の申請書類を整え、所轄の地方運輸局長または国土交通大臣へ登録・許可の手続きを行う必要があります。手続の全体像と各ステップで求められる主な書類・注意点について詳しく解説してまいります。
第一種 貨物利用運送事業 の登録手続
第一種貨物利用運送事業については、「登録制」が採用されており、以下の書類を整えて地方運輸局長に提出します(施行規則第4条第1項・第2項)。
登録申請書(様式第1号)
- 法第4条第1項に基づく申請であり、商号・所在地・代表者・業務の範囲等を記載。
登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地
三 事業の経営上使用する商号があるときはその商号
四 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲2 前項の申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
貨物利用運送事業法 第3条
添付書類の主な内容
- 事業計画書
- 実運送事業者との関係、保管施設の有無、業務内容を詳細に記載。 - 契約書の写し
- 実運送事業者と締結した契約書類(配送委託契約など)の写し。 - 施設関係書類
- 保管体制を有する場合は、面積・構造・附属設備まで記載。 - 法人関係書類
- 登記事項証明書、定款、役員名簿・履歴書、直近の貸借対照表。 - 個人申請の場合
- 財産調書、履歴書、戸籍抄本が必要。 - 欠格要件に該当しない旨の証明
- 法第6条第1項第1号~第5号に該当しないことを証する書面。
第一種貨物利用運送事業の登録を申請しようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載した事業の計画
イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
ハ その他事業の計画の内容として必要な事項二 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
三 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)四 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書五 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類六 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 財産に関する調書
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書七 法第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
3 国土交通大臣が必要ないと認めたときは、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。
貨物利用運送事業法施行規則 第4条
また、資産要件としては 300万円以上の純資産が求められ、貸借対照表から「資産−負債」の差額を評価します。創業費や営業権などの繰延資産は資産額に含まれない点にも注意が必要です。
法第六条第一項第七号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(「基準資産額」)が300万円以上であることとする。
貨物利用運送事業法施行規則 第7条
基準資産額は、貸借対照表又は財産に関する調書(「基準資産表」)に計上された資産の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。
貨物利用運送事業法施行規則 第8条
利用運送約款とその認可
運送契約に関する取扱条件は、標準的な約款を整備し、「認可申請」を行う必要があります。利用運送約款には以下の項目を記載しなければなりません。
- 利用運送機関の種類
- 運賃・料金の算出方法
- 損害賠償等に関する責任区分
- 荷物の引き渡し、保管方法 等
申請書には、新旧対照表や改正理由を記載することも求められます。
利用運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第一種貨物利用運送事業である旨及び利用運送機関の種類
二 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
三 利用運送の引受けに関する事項
四 受取、引渡し及び保管に関する事項
五 損害賠償その他責任に関する事項
六 その他利用運送約款の内容として必要な事項貨物利用運送事業法施行規則 第12条

第二種 貨物利用運送事業 の許可手続
第二種については「許可制」であり、より厳格な審査が行われます。申請時には「事業計画書」と「集配事業計画書」の2種を整え、内容に応じた多くの書類を添付します。
事業計画書の記載事項(施行規則第18条第1項)
- 利用運送機関の種類、利用運送の区域・区間、営業所の位置、業務範囲
- 保管施設の有無・概要(面積・構造・附属設備)
- 実運送事業者の情報、集配委託先の名称・住所・拠点 等
集配事業計画書(同第2項)
- 集配拠点の場所
- 地域ごとの対応範囲
- 営業所の名称・位置
- 使用自動車の台数、車庫・休憩施設の収容能力 等
特に、自動車を用いる集配業務がある場合は、運行管理体制を記載した書面や、自動運行システムに関する詳細情報が必須となります(施行規則第19条第1項第3号)。
事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 利用運送機関の種類
二 利用運送の区域又は区間
三 主たる事務所の名称及び位置
四 営業所の名称及び位置
五 業務の範囲
六 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
七 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
八 実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置2 集配事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 貨物の集配の拠点
二 貨物の集配を行う地域
三 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
四 貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 各営業所に配置する事業用自動車の数
ロ 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係るイに掲げる事項
ハ 自動車車庫の位置及び収容能力
ニ 事業用自動車の運転者、特定自動運行保安員及び運行の業務の補助に従事する従業員(「乗務員等」)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力五 貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数
貨物利用運送事業法施行規則 第18条
添付書類(施行規則第19条第1項)
- 実運送事業者との契約書
- 登記関係書類(法人の場合)
- 役員・設立者の履歴書
- 財産調書(個人の場合)
国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
二 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
三 自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者にあっては、次に掲げる書類
イ 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
ロ 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
ハ 特定自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類四 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書五 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類六 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 財産に関する調書
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書七 法第二十二条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
2 国土交通大臣が必要ないと認めたときには、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。
貨物利用運送事業法施行規則 第19条
許可を受ける前に確認したいポイント
- 自動車を使って集配を行う場合、貨物自動車運送事業法による別途許可が必要なケースもあるため、重複確認が必要。
- 法第22条に基づき、欠格事由がないことを証明する書類の提出も必須です。
共通の注意点
- 提出先の判断
第一種も第二種も、通常は所轄の地方運輸局長に提出しますが、内容によっては運輸支局長や海事事務所長を経由する必要があります。 - 約款は原則認可制
標準利用運送約款が定められている場合でも、自社オリジナルで作成する場合は必ず認可を受けなければなりません。
第一種・第二種ともに、添付書類の種類が多く、申請書類の整合性や形式的なミスによって補正指導や却下のリスクもあります。とくに創業直後の法人が行う場合、財務書類の作成や代表者の履歴書整備などにも時間を要するため、事前準備が重要です。
貨物利用運送事業 申請手続きについての行政書士報酬は
申請ALL.com ならチャットボットで自動でお見積りいたします。
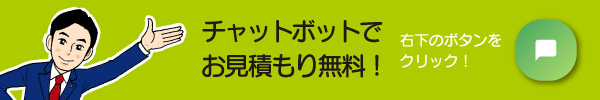
外国人事業者の注意点
貨物利用運送事業は、日本国内において外国法人や外国籍の個人が参入することも可能ですが、登録・許可の際には日本企業とは異なる追加的な書類や審査基準が設けられています。ここでは、外国人または外国法人が第一種または第二種貨物利用運送事業に参入する際の主な注意点を、関連条文とともに解説します。
外国人による 第一種 貨物利用運送事業
外国人や外国法人が、国際貨物運送を取り扱う 第一種貨物利用運送事業(外国人国際第一種)を営もうとする場合、通常の登録申請書類に加えて以下の事項を記載しなければなりません。
追加的な記載事項
- 法人:代表者および役員の国籍
- 出資比率(国籍別、国・公共団体・民間別に分類)
- 個人:国籍の明示
さらに、外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、登録拒否のリスクが本国の制度にも左右される点が特徴です。
登録拒否となる可能性
国土交通大臣は、申請者の所属国の制度や慣行が、日本との間で公正な事業活動を阻害すると認める場合、登録を拒否することができます。
たとえば、次のような場合には登録が認められないおそれがあります。
- 日本企業に対して不利な規制を敷いている国(報復措置的な登録拒否)
- 国際運送に関する二国間協定が不安定な国
- 貨物運送の法令が整備されておらず、透明性や信頼性に欠ける国
これはいわば「相互主義」の考えに基づくものであり、経済産業省や外務省と連携して判断されます。
国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由とする。
貨物利用運送事業法施行規則 第32条
外国人による第二種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業を外国人が行う場合、基本的な要件は日本企業と同様ですが、国籍や出資構造の開示義務が生じます。
許可申請書に記載すべき事項
- 代表者・役員の氏名と国籍
- 出資者の構成と比率
- 利用運送機関の種類や業務区域の詳細
- 事業計画の内容(施設、集配体制、実運送業者等)
実務上のポイント
- 翻訳文書の準備:登記簿謄本や定款などが外国語の場合、正確な日本語訳の添付が必要です。
- 国内代理人の設置:申請後の照会や補正対応を行うため、日本国内に常駐する連絡担当者を用意することが望まれます。
- 税務・外為法対応:出資者が海外に所在する場合、外国為替及び外国貿易法に基づく届出義務が発生することがあります。
外国法人による参入は、日系企業と比べて慎重な審査がなされるため、出資構造や法的安定性に配慮した事前準備が極めて重要です。行政書士の関与により、国籍や出資比率に基づく法的リスクの見通しを明確にすることが可能です。
変更・廃止・承継等に伴う手続
貨物利用運送事業は、登録や許可の取得後も、事業運営における重要事項に変更が生じた場合には、適切な届出や認可申請が必要です。また、事業の廃止や譲渡・承継が発生する場合にも、所定の手続が法律上求められます。ここでは、第一種・第二種の貨物利用運送事業者に共通する変更・廃止・承継等の主要な手続きを整理します。
登録事項の変更・届出
第一種貨物利用運送事業者は、登録後に以下のような内容に変更があった場合、変更登録の申請(認可)または変更届出が必要になります。
- 商号・住所・代表者の変更
- 取扱う運送機関の種類や事業区域の変更
- 利用運送契約先の変更 等
変更登録申請書には、変更理由、変更内容を明記し、変更に関係する添付書類も更新して提出する必要があります。
第二種貨物利用運送事業者の場合も同様に、事業計画や集配事業計画に関する変更には、認可申請または届出が求められます。
軽微な変更の例(施行規則第22条)
- 営業所名の変更
- 自動車の台数の変更
- 保管施設の構造の変更 等
これら軽微な変更については、事後届出で足りることが多く、提出すべき書類も簡素化されます。
事業の廃止・休止
事業を廃止または休止する場合は、所定の様式による届出が義務付けられています。これに違反すると、将来的な再開時や承継時に不利益を被ることがあります。
- 廃止届出:廃止日、理由、事業の内容を記載
- 休止届出:予定期間や理由を併記
休止中においても、再開する際は再度届出が必要となります。
役員変更・法人名称変更等の一般的な変更
役員変更・法人名称変更等の一般的なは、登録事項の変更届として、登記事項証明書の添付が求められます。代表権の有無によって提出期限が異なる場合もあり、注意が必要です。
正確な届出と手続を怠ると、業務停止や登録抹消などの行政処分の対象になることもあるため、変更が発生した場合は速やかに専門家に相談することをおすすめします。
貨物利用運送事業 開業手続きを行政書士に依頼するメリット
貨物利用運送事業の登録・許可申請には、多数の書類作成と法律に基づく厳密な手続が求められます。申請書・契約書・事業計画書・財務書類などの内容が法令に適合していない場合、不備として補正指示がなされることが多く、審査が長期化する原因にもなります。
こうした煩雑な手続に対して、行政書士に依頼することには以下のような具体的なメリットがあります。
① 添付書類の整備と法令要件の確認を一括対応
例えば、第一種の申請では定款、登記事項証明書、役員履歴書、財務諸表(貸借対照表)等の提出が必要です。一方、第二種ではさらに運行管理体制や自動運行装置に関する詳細資料などが求められ、誤った記載は差し戻しの原因となります。
行政書士は、これらの必要書類のチェックリストを活用し、法令の要求に即した形で収集・整備・作成を支援します。
② 約款認可などの専門的書面も対応
利用運送約款には、運送機関の種類・運賃・責任範囲・保管方法・損害賠償などの最低記載事項が定められており、一般の方が自己作成することは非常に困難です。
行政書士は、他の事業者の例を参考にしつつ、法定要件を満たした形で約款を作成し、認可申請書とともに提出します。とくに運賃や保管の責任の記載方法は審査上の重要点であり、プロの判断が求められます。
③ 地方運輸局とのやり取りを代行
登録や許可の申請は、地域を管轄する地方運輸局や運輸支局への書類提出・補正対応・質問対応を含みます。とくに「第二種」では事前相談や補正指示も多く、個人や法人代表者が対応すると本業に支障をきたす恐れがあります。
行政書士は、提出先とのやり取りを一括して代行し、必要な補足説明や追加資料の提出もスムーズに進めます。
④ 外国法人・外国人事業者との申請も対応可
外国資本が関与する場合、出資比率・代表者の国籍などを明記し、登録拒否事由に該当しないかの確認が必須です。行政書士は、日本語に不慣れな外国人事業者に対して、書類の翻訳や解説、国際ビジネス上のリスクを回避するためのアドバイスも提供できます。
まとめ
行政書士に依頼することで、法律に準拠した申請が可能になるだけでなく、審査の円滑化、補正の削減、手続き全体の迅速化が期待できます。自社のリソースを無駄にせず、専門家の力を借りて確実な許認可取得を目指しましょう。
貨物利用運送事業 行政書士見積もりが無料
貨物利用運送事業は、トラック・鉄道・船舶など複数の運送手段を組み合わせ、荷主の物流ニーズに応える現代的かつ柔軟なビジネスモデルです。しかし、事業開始にあたっては「第一種登録」「第二種許可」ともに、多くの書類作成と厳格な審査対応が求められます。事業計画、約款認可、運行体制の確認など、専門的な判断が必要な場面が多く、個人や社内対応では限界があります。
全国対応で行政書士が、第一種・第二種貨物利用運送事業の登録・許可申請をサポートしております。外国法人やグループ企業による参入、既存事業の拡張、事業譲渡・承継など、幅広いケースに対応可能です。
まずはお気軽に、チャットボットよりご相談ください。
行政書士費用見積を案内することができます。
貨物利用運送事業 申請手続きについての行政書士報酬は
申請ALL.com ならチャットボットで自動でお見積りいたします。
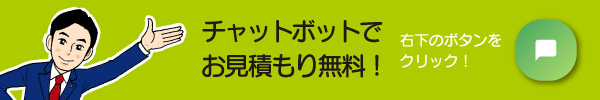
外国人で事業を開始される場合は、在留資格を経営管理に変更しなければならない場合もございます。
岡高志行政書士事務所で提供しておりますVISA取得見積もりサービス VISA de AI もご検討ください。

